
大阪中小企業診断士会は、2025年に設立40周年を迎えました。そこで今回は、40周年記念事業の第1弾として、理事長の池田朋之氏、前理事長の福田尚好氏による対談を実施。その模様を前編・後編に分けてお届けしています。
後編では、福田前理事長が全国本部の会長として実行された組織改革や、中小企業診断士が活躍するための考えなどをお話いただきました。前編はこちらよりご覧いただけます。
理事長 池田 朋之氏
プロフィール
| 1991年 | 独立開業・(有)池田経営コンサルタンツ設立 |
|---|---|
| 1993年 | 株式会社アソシエ 代表取締役 |
| 2011年~ | 流通科学大学非常勤講師 |
| 2013年~ | 大阪経済大学大学院非常勤講師 |
| 2019年~ | 中小機構近畿本部企業支援課管理者アドバイザー |
| 2023年~ | 中小機構近畿本部企業支援課シニアアドバイザー |
前理事長 福田 尚好氏
プロフィール
| 1970年 | 大阪市立大学商学部卒業 |
|---|---|
| 1970年 | 日本ビクター(株)入社 |
| 1988年 | 福田経営研究所設立 |
| 2003年 | 大阪市立大学大学院経営学研究科修了 |
| 2006年 | (株)プラクティカルマネジメント代表取締役 |
| 2010年 | 大阪経済大学大学院客員教授 |
| 2012年 | (一社)中小企業診断協会全国本部会長 |
| 2017年 | 旭日中綬章 受章 |
福田先生は大阪中小企業診断士会の理事長、そして中小企業診断協会大阪支部長として機能分化を推進された後、中小企業診断協会全国本部の会長にも就任されていますよね。
全国本部の会長になられた際には、まず組織改革に取り組まれたと伺いました。会長になられた経緯や、組織改革の内容をお聞かせいただけますでしょうか。
正直なところ、会長になる気はまったくありませんでした。正確に言うと「なれない」と思っていたんです。大阪よりも数多くの会員数がいる本部で、大阪の人間が会長になるとは到底想像もつきませんでした。
ですから、会長のお話をいただいても最初はお断りしていましたね。ただ、どうしても就任してほしいと依頼を受けたので、最終的に受けることにしました。
そうだったんですね。当時、全国本部には広い会長室があったそうですが、福田先生が会長に就任されてからは会議室に転用されたと伺いました。
その通りです。組織のトップとしての姿勢を見せなければ、信頼されないだろうと考えていました。東京よりも規模が小さい大阪支部の出身者ですから、発言力も限られます。だからこそ私自身が率先して、変える部分は変えようと思ったんです。
それが福田先生の「覚悟」だったんですね。しかし、会長に就任されたことを歓迎しない人もいたと伺いました。
今でも鮮明に覚えていますよ。仕方がありませんが、「なぜ大阪の人間が」と思う人もいたでしょうね。それでも、私の周りには応援してくれる方がたくさんいたので、大きな原動力になりました。
最初の3ヶ月ほどは大変でしたが、次第に東京の皆さんも協力してくれるようになり、改革を進めることができたんです。多くの皆さんの応援があってこそでしたね。
 2017年 旭日中綬章 受章時の記念講演
2017年 旭日中綬章 受章時の記念講演
福田先生は士会のトップも、そして全国のトップも務められました。中小企業診断士としてのお仕事に加えて、ほとんど無報酬で会の活動にも尽力されていたはずです。
中小企業診断士という資格のために、ここまで労力を割いて尽力された方は、他にお会いしたことがありません。当時の先生を突き動かす思いは、どこから生まれたのでしょうか。
正直なところ、私自身もなぜそこまでできたのか、今振り返ってもわからないんです。ただ、あの頃はまだ若くて、燃えていたのは確かですね。
中小企業診断士という資格を、他の士業に引けを取らない、一流の士業にしたい気持ちが強かった。その想いを胸に奔走していたと思います。
そこまでの熱意を持って改革されたのは、本当に尊敬の念しかありません。
いやいや、私だけの力じゃないですよ。多くの皆さんが応援してくださったおかげです。
改めて、組織のトップとして福田先生が心がけていたことは何でしょうか。
やはり、中小企業診断士という資格、そして士会のネームバリューを上げること。これが一番の目標でしたね。私の活動はその2点に集約されていたと言っていいかもしれません。
そのために、ご自身の生活や時間も投入されてきたと。
そうですね。政府の審議会に呼んでいただいて、東京まで足を運んでいた時期もあります。
私が福田先生を尊敬するもう一つの理由は、挨拶で周りを和ませるギャグを言われることもありますよね。とても私にはできないですね。
組織のトップは、挨拶を求められると固い内容になる方が多いと思うんです。でも福田先生は周りが和むようなギャグを言われた後に、大事な話を構成されますよね。私としても勉強になります。
集まっているのはプロの中小企業診断士ですからね。プロの前で、誰もが知っているような話をしても面白くないじゃないですか。
それよりも、ユーモアを交えつつ「皆で一緒にやろうじゃないか」という雰囲気を作るほうが良いと考えました。ただそれだけのことなんです。
ここからは未来の話になりますが、士会の今後、そして中小企業診断士という資格全体の将来性について、お考えをお聞きしたいです。特に、中小企業診断士がこれから活躍するためには、何が必要だとお考えですか。
我々の若い頃と違って、中小企業診断士は「専門性」を持たなければならないと思います。
もちろん、経営全般を知っているのは大前提ですが、その中でも「特にこの分野は任せてください」と言える専門性を磨くこと。これこそもっとも大事になるのではと考えています。
中小企業診断士は「ジェネラリスト」と言われることが多いですが、その中でも専門性が重要だと。
間違いなく必要ですね。専門性がなければ、安定して仕事を受注することは難しいと思います。
若い中小企業診断士が私のところに来た際に、「あなたの専門は何ですか?」と聞くと、「経営管理全般です」と答える人がいます。ただ、そう言われると私の中では記憶に残らないんですよ。
それに対して「販売管理が専門で、特に店舗ビジネスが得意です」と言われた場合は、具体性があって記憶に残ります。だから、後でそういった仕事が発生したときに「そういえばこの分野が得意な人がいたな」と思い出して、その人に仕事を依頼するケースもあります。
より具体的に、何が強いのか伝えてもらえると印象に残りますが、「全般です」と言われると本当に記憶に残りません。
仕事を発注する企業側も、きっと同じ感覚でしょうね。
そうだと思いますよ。企業も平均点が80点の人よりは、頼みたいことに対して100点を出せる人に頼みたいと思うはずです。
一つの分野で仕事をきっちりやっておけば、自然とその経験が他の分野に活かされて、仕事の幅が広がります。そうすると規模の大きな案件にも対応できるようになるんです。
経験の積み重ねが、結果として仕事の幅を広げるということですか。
そうです。大きな仕事を取れるようになってからが、本当の勝負だと思います。
若い方は、まず自分の専門性を高めることが先決。そして経験を重ね、専門性を極めていけば、結果として仕事の幅が広がっていくということですね。
最後に、士会の会員の皆様、これから中小企業診断士を目指す方々に向けて、何かメッセージをいただけますでしょうか。将来への展望も含めて、お考えを聞かせていただけたら幸いです。
私が常に思っているのは、中小企業診断士という資格そのものを将来的に「士業のトップにしたい」ということです。時間がかかる目標だとは思いますが、不可能ではないと考えています。
士業のトップ、ですか。大きな目標ではありますが、私としても実現させたいです。
中小企業診断士ほど、幅広い分野で活躍できる士業は他にないと思います。例えば、税理士なら税務、社労士なら労務など、それぞれ専門の分野がありますよね。ただ、診断士は経営全般のお手伝いができます。
とはいえ、一人ですべてをこなすのは簡単ではありません。だからこそ士会は、組織として「この分野ならこの専門家がいる」というように、どの分野にも専門家がいる集団になることが重要です。
専門性を持った個人の集合体として、総合力を高めるのが大切なんですね。
そうです。そうなれば組織として強くなれます。
全員が80点のジェネラリスト集団では、組織としても80点で終わってしまいます。しかし、Aという分野はこの人が100点、Bという分野はこの人が100点という専門家が集まれば、お客様に対して最大限の価値を提供できるんです。
そういうことができるのは、中小企業診断士しかいないと。
そう思います。専門家集団の集まりという組織を作っていけば、士業のトップになることも可能だと思いますね。
中小企業診断士は仕事の範囲が広く、報酬にも決まった制限がありません。ここまで自由度の高い資格も珍しいと思います。
確かにおっしゃる通りですね。中小企業診断士には、他の資格にないメリットがたくさんあるんです。だから、この資格を最大限に活用しないと損だなと思います。
資格の持つポテンシャルを最大限に引き出すことが重要だと。若い中小企業診断士や、これから中小企業診断士を目指す方々にも、福田先生のこの熱い思いと、専門性を磨くことの重要性を知っていただきたいと思います。
最後に、若い人たちには「1回のチャンスを大切にする」ことを伝えたいです。
受注金額が安くても、この程度でいいだろうという考え方は絶対ダメです。そう考えて仕事をすると、相手の記憶には残りません。一旦仕事を受けた限りは全力で取り組む。これが一番大事です。
最初のうちは、小さな仕事から始めるケースもあるでしょう。でも、そういった仕事でも、相手に評価してもらうチャンスであることに変わりはありません。そこで相手の期待を上回ることができれば、次はもっと大きな仕事につながります。
先生のその言葉、心に刻んでおきます。本当に福田先生がいなかったら、今の私はないと思います。
とんでもありません。今回は楽しいお話ができました、ありがとうございました。
本当に貴重なお話をありがとうございました。
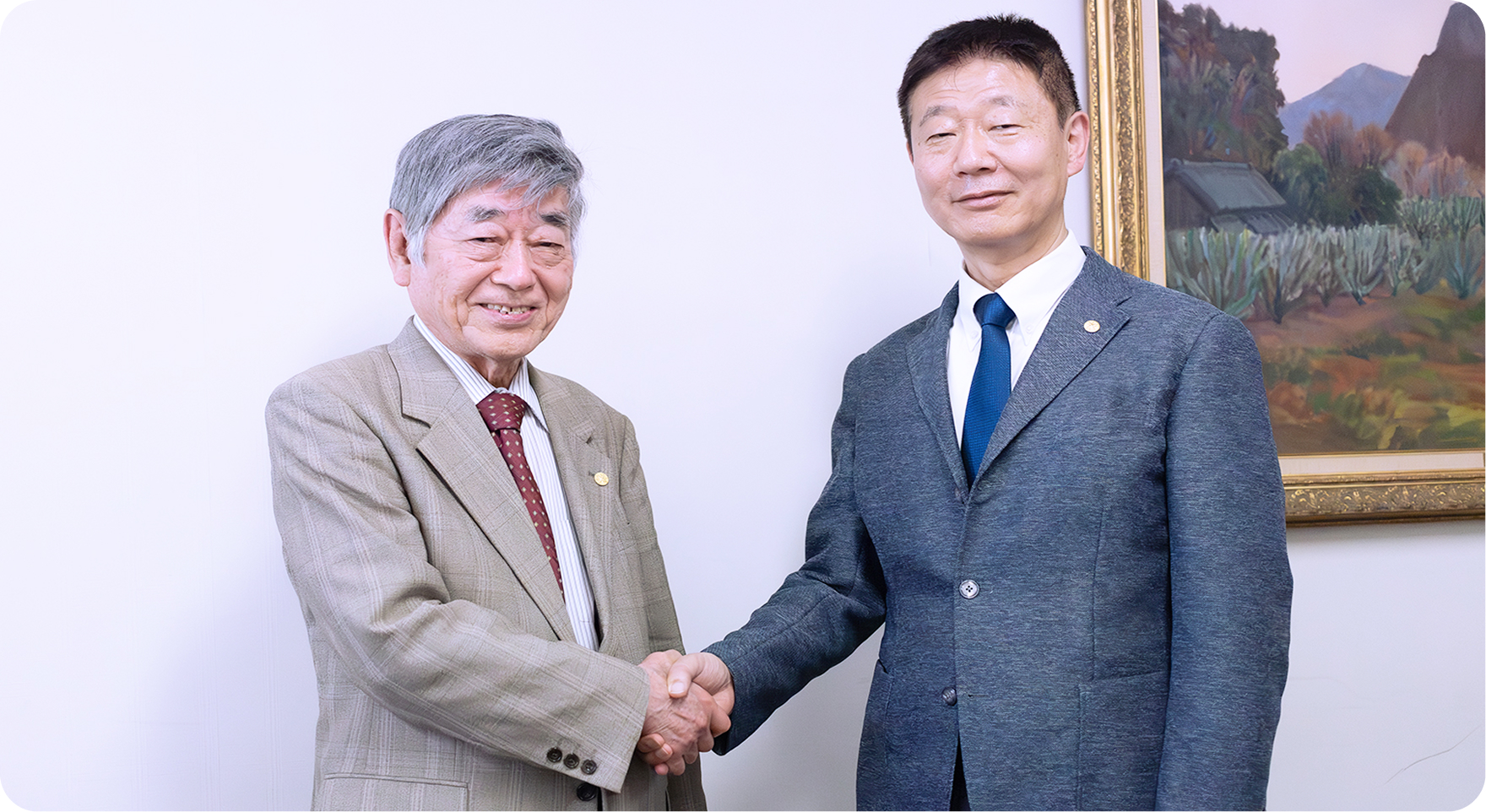
今回は40周年記念事業の第1弾として、理事長の池田朋之氏、前理事長の福田尚好氏による対談をお届けしました。
後編では福田前理事長の取り組みや、これからの中小企業診断士に求められる要素などを伺っていきました。「士業のトップにしたい」という目標のもと、今後もお客様への貢献を続けていきます。
ぜひ、大阪中小企業診断士会の今後にも注目いただければと思います。









